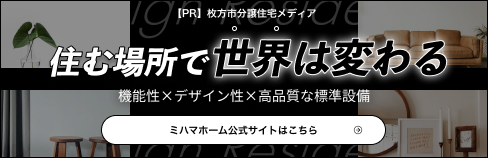「C値の基準ってどれくらい?」「C値って本当に重要なの?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。家づくりにおいて、「高気密・高断熱」という言葉はよく耳にすると思いますが、C値も住宅の気密性を示す重要な指標です。
C値が低いほど気密性が高く、快適で省エネな住まいを実現できます。高気密・高断熱住宅を理想としているのであれば、C値の基準について正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、C値の基準や重要性、具体的な数値、C値を上げる方法などをわかりやすく解説します。常に快適な住環境を保つ理想の住まいづくりを目指す方は、ぜひ参考にしてください。
なお、以下では枚方市でおすすめの会社を紹介しているので、あわせてご覧ください。
C値の基準とは?その意味と重要性
まず、C値とは「隙間面積」の割合を示す数値です。住宅の気密性能を表す指標であり、C値が低いほど隙間が少なく、気密性が高いことを意味します。
C値の計算方法
C値は以下のように算出されます。
【建物全体の隙間を合計した面積(c㎡)÷延べ床面積(㎡)】
たとえば、延べ床面積100㎡の住宅に、合計500cm2の隙間がある場合C値は5.0となります。ただし、実際にはすべての隙間を正確に測定するのは難しいため、気密測定機を用いて測定するのが一般的です。
気密測定はやり直しが生じることを考慮し、建築が完成する前の断熱加工を実施した段階で計測します。気密測定を依頼する際、多くの場合3~8万円程度の費用が必要です。
正式な気密測定を望む場合は、2回測定してもらうとより正確なC値を知ることができますが、費用も2倍になる点に注意が必要です。
C値の基準の考え方3つ
ここでは、C値の基準の考え方について、以下3点を深堀りしてより詳しく解説します。
以下でそれぞれ詳しく見ていきましょう。
①平成11年基準は5.0
C値は以前、基準値5㎠/㎡以下と基準が定められていました。しかし、いつの間にか基準がなくなり2009年(平成11年)の法改正以降明確な基準は設定されていないのが実情です。
②目指すC値は0が理想
C値は低ければ低いほど、気密性能の高さを表す数値です。目指すべき数値は「0」だといえますが、住宅でこの数値を実現するのは不可能だといわれています。
窓や玄関、排水、換気扇など空気が出入りする箇所は必ず存在するため、こういった隙間を考慮しながらできるだけ低いC値を目指すとよいでしょう。現状では、気密性を高める施工を得意としているハウスメーカーが容易に出せるC値の基準としては、C値0.7㎡以下とされています。
③換気の種類によってもC値は異なる
C値の基準は、採用する換気システムの種類によっても大きく異なるものです。もっとも計画的な換気が実現できるシステムが「第1種換気」で他に「第2種・第3種換気」が存在します。
24時間換気システムは、シックハウス症候群を防ぐため建築基準法で設置と稼働が義務付けられました。24時間換気をする必要があるため、必ず家の空気が外へ漏れていきます。
温めた空気、冷やした空気を外に逃さず効率的に換気する方法として有効なのが「熱交換型換気扇」です。C値は、採用する換気システムによっても差が生まれ、0にするのは現実的に難しいということを覚えておきましょう。
地域別のC値基準
地域の気候条件によってC値の目安は異なります。寒冷地では暖房効率を高めるためにより低いC値が求められ、温暖地では適度な気密性と通気性のバランスが重要です。
地域に適したC値を目指すことで、快適な室内環境と省エネ効果を最大限に引き出せます。ただし、地域を問わず、できるだけ低いC値を目指すことが理想的です。
住宅の性能や快適性を高めるためには、地域の気候特性を考慮したC値の基準を参考にしながら、適切な目標値を設定することが大切です。
位置と温暖地の違い
地域の気候条件によってC値の目標値は異なります。寒冷地では暖房効率を高めるために、より高い気密性能が求められます。
寒冷地ではC値1.0以下が目安で、北海道などではC値0.5以下を目指す事例もあります。温暖な地域ではC値2.0以下、多湿地域ではC値1.5~2.0程度が参考値です。
環境省の「住宅脱炭素NAVI」(2025年3月17日更新)によると、各自治体が独自に設定している基準値も存在します。以下にまとめましたので、参考にしてください。
| 自治体 | C値実測値 |
|---|---|
| 北海道(北方型住宅ZERO) | C値実測値1.0以下 |
| 札幌市(札幌版次世代住宅基準) | 新築住宅:C値実測値0.5以下改修住宅:C値実測値1.0以下 |
| 宮城県(みやすま 健康省エネラベリング) | 高気密化に努めること |
| 山形県(やまがた 省エネ健康住宅) | C値実測値1.0以下 |
| 山形県(やまがた 省エネ健康住宅) | C値実測値1.0以下 |
| 長野県(信州健康ゼロエネ住宅) | C値実測値1.0以下 |
| 新潟県(雪国型ZEH) | C値実測値1.0以下 |
| 東京都(東京ゼロエミ住宅) | C値実測値1.0以下 |
| 鳥取県(とっとり健康省エネ住宅) | C値1.0以下 |
2025年4月から省エネ基準適合が義務化されていますが、C値については明確な数値基準は設けられていません。多くの自治体や高性能住宅では実測値1.0以下を目安としています。
C値が光熱費や快適性に与える影響
C値は住宅の光熱費や快適性に大きな影響を与えます。C値が低いほど高気密な住宅であると証明でき、以下のようなメリットがあります。
それぞれの影響を詳しく見ていきましょう。
1.光熱費を削減できる
C値が低く高気密な住宅は、魔法瓶のように室内の熱を逃がしにくく、外の冷気も入りにくいのが特長です。熱が逃げないことでエアコンなどの冷暖房効率が格段に向上します。
夏は涼しい空気を、冬は暖かい空気を逃がさないので、設定温度を低め、あるいは高めに設定しても快適に過ごせる点がメリットです。結果として、冷暖房の使用頻度や稼働時間が減り、大幅な光熱費の削減につながります。
2.年間を通して快適な住環境を保てる
高気密住宅は、断熱性も高いため、外気温の影響を受けにくく、夏は涼しく、冬は暖かい室内環境を保てます。一年中春のような、快適な温度で過ごせるイメージです。
また、高気密住宅では計画的な換気システムが導入され、室内の空気を常にきれいに保てることがほとんどでしょう。新鮮な空気を循環させれば、カビやダニの発生も抑制され、健康的な暮らしを送れる点もメリットだといえます。
3.防音効果が高まる
C値が低い高気密住宅では、外部からの騒音が室内に入りにくくなり、防音効果が高まります。隙間が少ないため、音が伝わる経路が減少し、静かな住環境を実現できる点も魅力です。
特に交通量の多い道路沿いや、飛行機の航路下など、騒音が気になる立地では、高気密住宅の防音効果は大きなメリットとなります。また、室内の音が外に漏れにくいため、楽器の演奏や映画鑑賞なども周囲に気兼ねなく楽しめるでしょう。
防音効果は生活の質を向上させる重要な要素であり、C値を下げることで得られる副次的なメリットの一つです。
C値とUA値の関係
C値とUA値は、住宅の性能を評価する上で重要な指標です。C値が気密性を表すのに対し、UA値は断熱性能を示します。両者はそれぞれ異なる性能を評価するものですが、相互に関連しています。
高性能な住宅を実現するためには、C値とUA値の両方を適切な水準に保つことが重要です。気密性が高くても断熱性が低ければ、結露やカビの発生リスクが高まります。逆に断熱性が高くても気密性が低ければ、熱損失が大きくなります。
快適で省エネな住まいを実現するためには、C値とUA値のバランスを考慮した設計・施工が必要です。
UA値とは
UA値は「外皮平均熱貫流率」と呼ばれ、住宅の断熱性能を示す指標です。UA値は、「UA値=建物の熱損失量の合計÷延べ外皮面積」という計算式で求められます。
つまりUA値は、外皮(建物の表面)1㎡当たりで、平均して何Wの熱が逃げるかを算出したものです。UA値が低いほど断熱性能が高く、熱の出入りが少ないことを意味します。
C値が「隙間からの空気の出入り」を評価するのに対し、UA値は「壁や窓などを通しての熱の伝わりやすさ」を評価します。両者は異なる性能を測る指標ですが、どちらも住宅の省エネ性能に大きく影響します。
UA値の地域別基準
UA値には国が努力目標として定めた基準値があり、地域区分ごとに異なる値が設定されています。この基準は「省エネ基準」と呼ばれ、2025年4月から義務化されます。
日本は8つの地域区分に分けられており、それぞれに適したUA値の基準が定められています。寒冷地ほど厳しい(低い)基準値が設定されています。
以下に、地域区分ごとのUA値基準を示します。
| 地域区分 | 主な地域 | UA値基準(W/㎡・K) |
|---|---|---|
| Ⅰ地域 | 北海道 | 0.46 |
| Ⅱ地域 | 青森県 岩手県 秋田県 | 0.46 |
| Ⅲ地域 | 宮城県 山形県 福島県 栃木県 新潟県 長野県 | 0.56 |
| Ⅳ地域 | 茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 富山県 石川県 福井県 山梨県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 | 0.75 |
| Ⅴ地域 | 宮崎県 鹿児島県 | 0.87 |
| Ⅵ地域 | 沖縄県 | 0.87 |
UA値が小さいほど熱が逃げにくく、断熱性能が高いことを意味します。たとえば、北海道のような寒冷地では低いUA値(高い断熱性能)が求められる一方、温暖な地域ではやや緩やかな基準が設定されています。
C値とUA値の両立が重要
住宅の性能を高めるためには、C値(気密性)とUA値(断熱性)の両方を適切な水準に保つことが重要です。どちらか一方だけが優れていても、十分な効果は得られません。
例えば、UA値が低く断熱性が高くても、C値が高く気密性が低ければ、隙間から冷気が入り込み、暖房効率が下がります。逆に、C値が低く気密性が高くても、UA値が高く断熱性が低ければ、壁や窓を通して熱が逃げてしまいます。
両者をバランスよく向上させることで、初めて快適で省エネな住環境を実現できます。特に高気密・高断熱住宅を目指す場合は、C値とUA値の両方に配慮した設計・施工が必要です。
2025年4月から省エネ基準が義務化される
2025年4月から、原則すべての新築建物で省エネ基準への適合が必須となります。これは、脱炭素社会の実現に向けた国の取り組みで、建物のエネルギー効率向上が目的です。
改正により、建築確認時に省エネ基準の審査が加わり、基準を満たさなければ着工できません。エネルギー消費量や断熱性が評価され、手続きは複雑化する可能性がありますが、環境負荷の低減や光熱費削減、快適な住環境といった利点も期待されます。
増改築も対象となり、将来的にはZEH水準への基準引き上げも計画されています。
C値を上げるためにできることは?
C値を上げる、つまり住宅の気密性を高めるためには、以下の3つのポイントを押さえましょう。
それぞれの内容を以下で詳しく解説します。
断熱性と気密性を高める
高性能な断熱材を採用して断熱性を高めるのは、C値を下げるために非常に効果的です。断熱材は、熱の移動を遮断するだけでなく、空気の移動も抑制する役割を果たします。
壁や天井などに隙間なく断熱材を充填すれば、気密性を高め、C値を効果的に下げることにつながります。また、気密性を高めるためには、建物の構造材の接合部や配管などの貫通部分に適切な気密処理を施すことも重要です。
窓や玄関を工夫する
窓や玄関は、住宅の中でも特に隙間が生じやすい箇所であるため、気密性の高い窓や玄関を採用する必要があります。たとえば窓は、複層ガラスやトリプルガラスなど、断熱性能の高い窓を選びましょう。
窓枠の素材や構造も気密性に影響するため、アルミサッシよりも樹脂サッシの方がおすすめです。
高性能住宅を手掛ける施工会社に依頼する
高性能住宅の施工には、C値を適切に測定し、気密性の高い住宅を建てるため専門的な知識や技術が必要です。実績のある高性能住宅の施工実績が豊富な施工会社に依頼する必要があります。
そのため、過去の施工事例などを確認し、高気密・高断熱住宅の施工経験が豊富な会社を選びましょう。複数の会社を比較検討し、実績や技術力、費用などを総合的に判断すれば信頼できる施工会社を見つけられるはずです。
理想のC値を満たす高性能住宅を建てるなら「ミハマホーム」
ここまで「C値の基準」について解説しましたが、大阪近郊で気密性の高い高性能住宅を建築するなら「ミハマホーム」をぜひご検討ください。ミハマホームは、枚方市で創業55年、地域密着型の住宅会社です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | ミハマホーム株式会社 |
| 所在地 | 大阪府枚方市牧野阪2丁目8番2号 |
| 公式サイト | https://www.mihama-jutaku.co.jp/granz-equipment/ |